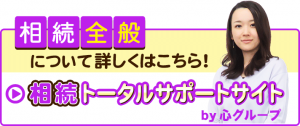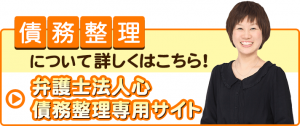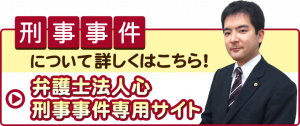ブログ
情状証人の尋問について
最近、刑事弁護人として受任した事件の公判で、証人尋問を行いました。
事実関係を争わない事件であり、立証趣旨は情状関係、証人になってもらったのは被告人の父・・・(続きはこちら)
速度違反事件の弁護活動
遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
昨年末から弁護士業務がこれまで以上に忙しくなり、今年に入ってか・・・(続きはこちら)
他人の名前をかたった取調べ
12月も後半になってきました。
2025年は大阪万博もあり、弁護士業務も忙しかったこともあり、例年よりも早く日々が過ぎているような気がします。
この時期・・・(続きはこちら)
上告の手続き
大阪高裁に控訴していた刑事事件について、判決が出ました。
現在、その内容について、上告すべきかどうか、弁護士として、依頼者と検討しているところです。
・・・(続きはこちら)
被害弁償に上乗せする慰謝料
大阪も最近は涼しくなりました。
まだ、弁護士事務所まで半袖シャツで通勤していますが、そろそろ長袖のシャツに着替える方がよいかもしれません。
ところで・・・(続きはこちら)
道頓堀川への飛び込みについて
今日、自宅の最寄り駅から大阪市内の弁護士事務所まで通勤中、昨日優勝を決めた阪神タイガースの優勝記念セールが行われているのを見ました。
ところで、阪神が優・・・(続きはこちら)
控訴審の流れ
弁護士として刑事事件の弁護活動を行っている事件の中に、大阪高等裁判所に控訴した事件があります。
これから、一般的な刑事事件の控訴審の流れについて説明しま・・・(続きはこちら)
最初の事件
現在、私は大阪の事務所で弁護士として執務していますが、その前は検事として全国各地で執務しておりました。
検事になって初めて担当した事件は、外国人の不法在・・・(続きはこちら)
不作為犯
弁護士として大阪で執務している際、不作為犯の成否について検討する機会がありました。
不作為犯について検討するのは司法試験の勉強をしていた時以来であり、実務・・・(続きはこちら)
債務整理の相談
大阪の事務所で弁護士として相談を受ける事件には、これまでお話しした刑事事件のほかにも、相続関係の事件や債務整理関係の事件等があります。
一口に債務整理とい・・・(続きはこちら)