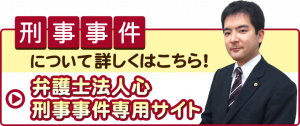保釈許可決定が出た後の流れ
刑事弁護の依頼を受けていた事件に関し、大阪地方裁判所に対し、被告人の保釈請求をしたところ、保釈許可の決定を得ることができました。
保釈許可の決定が出たからといって、自動的に被告人の身柄が解放されるわけではありません。
ここでは、弁護士としての備忘録も兼ねて、大阪地方裁判所で保釈許可の決定が出た後の流れについてまとめておきます。
保釈許可の決定が出ると、裁判所からその旨連絡を受けますので、弁護人は、裁判所の公判係属部の事務室で、保釈許可の決定書と、保釈保証金を納める際に提出する保管金提出書を受け取ります。
また、弁護人は、被告人の家族にも連絡を取る必要があります。
被告人の家族は、被告人のことをとても心配し、一日でも早く身柄を解放するように求めていました。
他方、被告人の家族に、保釈保証金の用意や、身柄が解放された後の被告人の迎えを準備してもらうためにも、連絡を取る必要があります。
その後、被告人の家族に用意してもらった保釈保証金を受け取り、裁判所の出納第一課まで行き、先ほどの保管金提出書と共に保釈保証金を提出しました。
出納第一課では、繰り返し、計数機を使うなどして保釈保証金が数えられ、保釈保証金の額に間違いがないことを確認された後、保釈保証金を預かったことを証明する保管金受領証書を受け取りました。
保釈保証金は、判決が確定すれば還付されますが、それまで、保管金受領証書は大切に保管しておかなければなりません。
なお、裁判所は、通常、午後5時で執務が終わるので、午後5時を過ぎると保釈保証金を預かってもらえなくなる可能性があります。
そうなると、被告人の釈放が翌日以降にずれこむことになります。
そこで、午後5時を過ぎてから保釈保証金を持ち込む可能性がある場合、あらかじめ裁判所に対し、その旨連絡し、出納第一課の方々に待っていてもらうように頼んでおく必要があります。
今回も、保釈保証金を用意して裁判所に持ち込む時間が午後5時を過ぎる可能性があったので、あらかじめ、裁判所に対してそのことを連絡し、出納第一課の方々に待ってもらっていました。
また、事前に登録しておくと電子納付の手続で保釈保証金を納めることも可能ですが、その際も、午後5時を過ぎて電子納付の手続を取ると、事務手続きが翌日扱いとなり、被告人の釈放が翌日以降にずれ込むことになります。
保釈保証金の納付が確認された後、裁判所から検察官にその旨の連絡がなされます。
その際、検察官は、被告人を釈放する旨の指揮をします。
その指揮を受けて、初めて被告人の身柄は解放されます。
被告人は、待っていた家族と合流し、久しぶりに自宅に帰ったのでした。