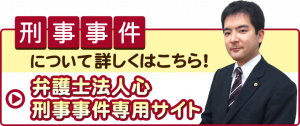被告人質問について
最近、弁護士として大阪で依頼を受けた被告人について、被告人質問を行いました。
被告人質問は、刑事裁判の手続において、被告人に対して弁護人、検察官及び裁判官が質問をする手続です。
被告人にとっては、質問に対する回答という形式ですが、起訴された事実について、認否をした後で詳しく具体的に主張することができる唯一の機会になります。
仮に、起訴された事実を否認するなどして犯罪の成立を争うような場合には、被告人が主張する筋立て(いわゆるアナザーストーリー)にそう内容を被告人質問で詳細に述べる必要があります。
そのためには、事前に被告人と弁護人との間で、どのような筋立てをするのか、その筋立てにそって弁護人がどのような質問をして、被告人がどのように回答するのか、検察官や裁判官からの質問を予想してどのように答えるのがよいのか、などについて、繰り返して何回も打ち合わせをする必要があります。
特に、被告人が勾留されている場合には、弁護人が接見する機会にしか打ち合わせをすることができないので、被告人にとって相当な負担になります。
一方、起訴された事実を認める場合でも、事前に被告人と弁護人との間で、被告人質問について綿密に打ち合わせをしておく必要があります。
そのような場合でも、事実関係を争わないにしても、被告人に有利な情状があることを裁判で明らかにする貴重な機会であることには変わりがありません。
被告人に有利な情状としては、例えば、事実関係を認めて反省をしていること、弁償や示談の話し合いが行われていること、同じような罪を再び犯すことがないように自動車の運転を控えたり運転免許を返納したりするなどの取り組みをしていること、社会復帰後に薬物依存の治療を受けたり薬物依存からの回復をサポートする団体に入ったりすることといった内容が挙げられます。
また、検察官や裁判官からの質問を予想してどのように答えるのがよいのかを検討しておくことは、そのような場合でも大事なことになります。