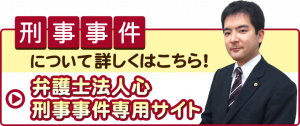少年事件の手続
弁護士として大阪でご相談を受けている際に、未成年が被疑者になる刑事事件の相談を受けたことがありました。
未成年による刑事事件は、少年事件と呼ばれ、成人による刑事事件とは別に、少年法によって手続等が規定されています。
捜査段階では、少年は成人と変わらず、警察官や検察官による取調べを受けるなどして、事件に対する捜査が行われます。
また、少年も、成人と同様に逮捕され、留置施設に勾留されるなど、身柄を拘束されることがあります。
なお、少年については、身柄を拘束される際に、勾留に代わる観護措置が講じられることがあります。
勾留に代わる観護措置では、少年鑑別所で10日間観護措置を受けます。
捜査が終わると、原則として、少年事件は全部の事件が家庭裁判所に送致されます。
成人の事件だと、起訴猶予や嫌疑不十分などの理由で不起訴処分になり、起訴されないことも多々ありますので、原則として家庭裁判所に送致されることは、少年事件の手続の大きな特徴です。
これに関して、被害者のいる事件での弁護活動として示談交渉が行われることが多く、成人の事件では示談交渉がまとまると起訴猶予により不起訴処分になることがよくあるのに対し、少年事件では示談交渉がまとまったからといって家庭裁判所に送られないことは、基本的にありません。
ですので、成人事件では示談交渉を捜査段階の間に早急にまとめることも多いのですが、少年事件では、形だけの被害弁償を急ぐよりも、少年自身の真の反省や謝罪の気持ちを十分に引き出し、それに基づいた示談交渉をすることが重視されます。
家庭裁判所に送致されると、少年鑑別所に収容されて、通常4週間の観護措置がとられることがあります。
また、家庭裁判所調査官により、少年や保護者または関係者の行状、経歴、素質、環境等について調査が行われます。
その上で、少年審判が行われ、少年の処分が決められます。
少年審判では、原則として検察官が立ち会うことはなく、裁判所が自ら主導して事件の調査や審理を行います。
少年の処分は、保護処分として少年院送致、児童自立支援施設等送致、保護観察又は不処分のいずれかになります。
なお、一定の重大な犯罪の場合や少年が成人になった場合は、少年に成人の刑事裁判を受けさせるために、検察官送致の処分がされることがあります。