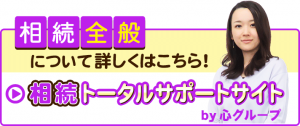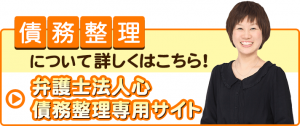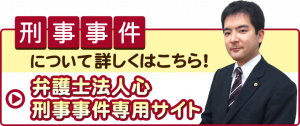控訴審についての覚書き
昨年秋に大阪高裁に控訴した刑事事件について、控訴審の公判期日が近づいてきました。
刑事事件の弁護士として受任しており、控訴審の準備も追い込みにかかっています。
ここで、改めて刑事事件の控訴審について、その手続をまとめておきます。
控訴審は、法律審かつ事実審であり、地裁での原判決の当否を事後的に審査して判断する事後審としての性格を持ちます。
控訴審は、地裁が裁判員裁判や裁判官1人のみの裁判であったとしても、裁判官のみで構成される合議制の裁判であり、最後の事実審です。
また、事後審であることによる控訴審の特徴として
① 裁判所が原判決の当否を審査するものであり、原則として裁判官が自ら事件の心証形成をしないこと
② 審査の判断基準時が原判決の言渡し時であり、原則として、判断資料は第一審が用いた資料に限定されること
③ 例外として、原判決を破棄する場合は、原審の口頭弁論終結時からさらに審理を続行し、自ら事実の認定をして判決すること
にあるとされています。
それらの特徴は、控訴審の公判手続きにも影響しています。
控訴審の公判手続きは人定質問から始まります。
続いて、控訴をした検察官又は弁護人によって控訴趣意書に基づく弁論が行われ、通常は、「控訴趣意書記載のとおり」と短く述べられます。
それに対し、相手側が弁論をします。
相手方が控訴趣意書に対して答弁書を提出している場合は「答弁書記載のとおり」と短く述べるのが通常です。
答弁書を提出していない場合は、口頭で反論を簡潔に述べるか「本件控訴は理由がなく、控訴棄却が相当である」と短く述べるのが通常です。
その後、事実の取調べが行われます。
事実の取調べは、通常、控訴趣意書の提出と同時に、事実取調べ請求書と証拠の写しを提出し、請求します。
もっとも、先ほど述べた控訴審の事後審的性格から、事実の取調べ請求が認められず、請求した証拠が却下されることがほとんどであると言われています。
この点から、原審段階で証拠提出や主張をもれなくしっかりと行っておく必要性は高いと言えます。
事実の取調べが行われた後、その結果に基づいて弁論を行います。
その際、事実の取調べに関連した控訴理由について、意見を述べることになります。
控訴審は、事件の大多数が第1回の公判期日で終結して、判決宣告期日が決められます。
大阪高裁では、1回の公判期日について20分から30分程度が割り当てられています。