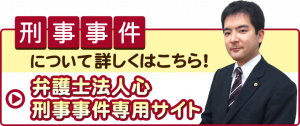- トップ
- ブログ
ブログ
保釈許可決定が出た後の流れ
刑事弁護の依頼を受けていた事件に関し、大阪地方裁判所に対し、被告人の保釈請求をしたところ、保釈許可の決定を得ることができました。
保釈許可の決定が出たからといって、自動的に被告人の身柄が解放されるわけではありません。
ここでは、弁護士としての備忘録も兼ねて、大阪地方裁判所で保釈許可の決定が出た後の流れについてまとめておきます。
保釈許可の決定が出ると、裁判所からその旨連絡を受けますので、弁護人は、裁判所の公判係属部の事務室で、保釈許可の決定書と、保釈保証金を納める際に提出する保管金提出書を受け取ります。
また、弁護人は、被告人の家族にも連絡を取る必要があります。
被告人の家族は、被告人のことをとても心配し、一日でも早く身柄を解放するように求めていました。
他方、被告人の家族に、保釈保証金の用意や、身柄が解放された後の被告人の迎えを準備してもらうためにも、連絡を取る必要があります。
その後、被告人の家族に用意してもらった保釈保証金を受け取り、裁判所の出納第一課まで行き、先ほどの保管金提出書と共に保釈保証金を提出しました。
出納第一課では、繰り返し、計数機を使うなどして保釈保証金が数えられ、保釈保証金の額に間違いがないことを確認された後、保釈保証金を預かったことを証明する保管金受領証書を受け取りました。
保釈保証金は、判決が確定すれば還付されますが、それまで、保管金受領証書は大切に保管しておかなければなりません。
なお、裁判所は、通常、午後5時で執務が終わるので、午後5時を過ぎると保釈保証金を預かってもらえなくなる可能性があります。
そうなると、被告人の釈放が翌日以降にずれこむことになります。
そこで、午後5時を過ぎてから保釈保証金を持ち込む可能性がある場合、あらかじめ裁判所に対し、その旨連絡し、出納第一課の方々に待っていてもらうように頼んでおく必要があります。
今回も、保釈保証金を用意して裁判所に持ち込む時間が午後5時を過ぎる可能性があったので、あらかじめ、裁判所に対してそのことを連絡し、出納第一課の方々に待ってもらっていました。
また、事前に登録しておくと電子納付の手続で保釈保証金を納めることも可能ですが、その際も、午後5時を過ぎて電子納付の手続を取ると、事務手続きが翌日扱いとなり、被告人の釈放が翌日以降にずれ込むことになります。
保釈保証金の納付が確認された後、裁判所から検察官にその旨の連絡がなされます。
その際、検察官は、被告人を釈放する旨の指揮をします。
その指揮を受けて、初めて被告人の身柄は解放されます。
被告人は、待っていた家族と合流し、久しぶりに自宅に帰ったのでした。
保釈請求について
先日、刑事弁護の依頼を受けていた事件に関し、大阪の裁判所に対して、被告人の保釈請求をしました。
保釈は、弁護士が、被告人の身柄を解放するために行うことができる手続の一つであり、勾留中の被告人が、保証金を納めることで身柄拘束を解いてもらうことができるというものです。
弁護人は、裁判所に対し、勾留中の被告人について、法律上、保釈することができない事情がないことのほか、裁判所の裁量によって保釈することが相当であることを理由に挙げて、保釈を請求します。
裁判所は、保釈の請求を受けた後、検察官に対し、被告人について保釈の請求があったことを通知し、意見を求めます。
それに対し、検察官は、被告人を保釈することについて意見を返します。
通常、検察官は、被告人を保釈することについて「不相当」か「相当」、又は「しかるべく」と意見を返します。
「しかるべく」というのは、裁判所の判断に任せるという意味です。
また、検察官は、「不相当」の意見を返す場合には、その理由を明らかにします。
その場合、検察官は、勾留中の被告人には法律上、保釈することができない事情があることや、裁判所の裁量によっても保釈することが相当ではないことを理由に挙げて、保釈をしないように意見することが通常です。
裁判所は、検察官の意見を受けて、保釈を許可するかを決定します。
裁判所が保釈を許可した場合、納める保証金の額も併せて決められます。
保証金の金額は、100万円単位になることが多いです。
また、その場合、被告人の制限住居や面会相手の制限等の条件についても、併せて決められます。
被告人は、保証金が納付されると釈放されます。
一方、保釈が許可されなかった場合には、弁護人は、裁判所に不服を申し立てることができます。
その場合、裁判所が決定した保釈の不許可について、維持すべきか又は取り消して被告人に保釈を許可すべきかどうかについて、より上位にある裁判所が再び判断をすることになります。
その結果、裁判所の判断が覆り、保釈が許可される可能性があります。
まとまった金額の保証金を用意する必要はありますが、被告人の身柄拘束を解く手段として、弁護士による保釈請求はよく利用されています。
交通事故の公判弁護
先日、大阪の裁判所で行われた、交通事故の刑事裁判で、公判弁護をしました。
事実関係自体には争いなく、公判は1回で結審しました。
とはいえ、弁護士としては、依頼を受けた被告人に少しでもプラスになる情状を公判で示し、マイナスになる情状についても少しでもフォローして、執行猶予付きの判決など、被告人に少しでも有利な判決を求める必要があります。
そのためには、事前に被告人とよく打ち合わせをするなどして、事前準備をする必要があります。
例えば、被告人に有利な情状として
〇 交通事故を起こした時に運転していた自動車を廃車にした
〇 運転免許が取り消された
〇 交通事故でけがを負わせた人の治療代は、かけていた保険から出ている
〇 今後、同居の家族が、交通事故を起こさないように被告人を監督する
といった事情が挙げられる場合、それぞれ証拠を用意する必要があります。
例えば、被告人が事故車両を廃車したのであれば、事故車両の廃車証明や抹消登録、被告人が運転免許を取り消されたのであれが、公安委員会が発行した運転免許の取消決定書を用意する必要があります。
また、交通事故の被害者に対する支払いの関係では、被告人がかけていた損害保険の証券や、損害保険会社が発行した支払いの明細書といった書類を用意する必要があります。
そして、家族による監督の関係では、監督してもらう家族に、今後被告人を監督することを約束する内容の手紙を書いてもらうことや、証人として、被告人を監督することを裁判で証言してもらうことが考えられます。
家族に証人として出てもらう場合は、事前に家族に証人として出てもらうことについて承諾を得たうえ、証人尋問ではどう話せばよいかについて打ち合わせをしたり、予行練習をしたりしておくことが必要になります。
さらに、被告人とは、被告人質問について打ち合わせをし、弁護人が質問しておく内容のほか、検察官や裁判官から質問されると思われる内容についても、どのように話をすればよいか、予行練習しておく必要があります。
そのような事前準備を経て、公判弁護に臨むことになります。
不起訴処分と起訴猶予について
刑事弁護の依頼を受けていた刑事事件の被疑者が不起訴処分になりました。
不起訴処分になると、検察官から被疑者が不起訴処分になったという内容の告知書を受け取ることができるため、被疑者を担当していた検察官に連絡して、被疑者の不起訴処分の告知書の発行を依頼しました。
すると、数日後、検察官から、検察庁の書式による、不起訴処分告知書が送られ、被疑者が不起訴処分になったことを、書面でも確認することができました。
被疑者が不起訴処分になったことにより、弁護士として依頼を受けた責任を果たすことができたと思っています。
ところで、不起訴処分とは、検察官が行う処分のうち、被疑者を起訴しないという処分を言います。
そして、不起訴処分になる理由の多くは、起訴猶予になります。
起訴猶予というのは、犯罪を認定する事実が明らかな場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により、被疑者を起訴する必要がないと検察官が判断した場合のことを言います。
検察官が起訴猶予にするかどうかについては、そのような被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況等をよく検討して、判断することになります。
検察官が起訴猶予の判断をするに当たって、犯罪後の情況に関する事柄については、被疑者の反省の有無、謝罪や被害回復の努力、又は逃亡や証拠隠滅の行動、環境の変化、社会的制裁の有無、身柄引受人その他の将来被疑者を監督する者や保護者の有無などの、環境調整の可能性の有無のほか、被害弁償の有無や示談の成否、被害感情等が問題となります。
今回の事件では、大阪の事務所から出て被害者と会うなどして示談交渉をして、被害者との間で示談を取りまとめることができましたが、示談の成否は、先ほど述べた事情の中では犯罪後の情況に関係することになります。
今回の事件に限りませんが、被害者がいる犯罪では、被害者との示談は、検察官が起訴猶予するかどうかを判断する際に、重視されるところであり、刑事弁護でも力が入れられているところです。
被害者との示談交渉も含めて、刑事事件の弁護について気になる点がありましたら、お気軽にご相談ください。
示談交渉を持ち掛けられたら
被害者との示談交渉は、刑事弁護人の重要な役割の一つです。
刑事弁護人の立場からすると、被害者との示談をまとめることで、被疑者の処分を免れ、又は軽減させることを目的としており、そのために被害者に大阪の事務所まで来てもらったり、被害者の許に伺ったりして示談に関するお話しをすることになります。
一方、被害者の立場からすると、これまで被害に遭わせた犯人を許せないと思っていたところ、弁護士から示談してほしい、犯人を許してほしいなどと持ち掛けられるのですから、どうすればいいのやら困惑することもあると思います。
実際に、私も、検察官だった時、捜査や公判を担当していた被害者から、弁護士から示談を持ち掛けられたけれど、どうすればよいかなどと相談を受けたことが何度もありました。
その際、私は、検察官という公務員の立場で示談を勧めたり勧めなかったりすれば中立性を害してしまうので、示談を勧めたり勧めなかったりするような回答はしませんでした。
もっとも、被害者が示談に応じれば受け取る示談金は、民事事件でいえば不法行為に基づく損害賠償に当たるものですので、被害者が示談に応じた上で示談金を受け取ることは当然のことであり、問題がないことはお話ししていました。
そのような話は、私に限らず、多くの検察官がお話ししていたと思います。
また、私がそのようにお話しすると、多くの被害者から、示談に応じれば犯人に有利になってしまうのではないか、犯人が不起訴になってしまうのではないか、などとご質問を受けることがありました。
確かに、検察官の立場からしても、示談がまとまることで被疑者が不起訴になるかどうかはともかく、被害者に謝罪も弁償もせずに放置しているよりも、示談により謝罪や弁償をする方が、被疑者には有利になることは、そのとおりです。
私は、被害者に対して、示談がまとまることで被疑者に有利になる可能性があること、その上で示談交渉に応じるかどうかは自由であることをお話ししていました。
では、弁護士の立場だと、被害者から示談交渉に応じるべきか相談を受けたらどう答えるべきでしょうか。
通常は、被害者のお考えやお気持ちをよく伺って、それに沿ったお答えをすることになるのでしょうが、私なら、示談交渉に応じる方向でお答えするのだろうと思います。
なぜなら、被疑者が被害者との示談をまとめようとするのは、被疑者の処分を免れ、又は軽減させることを目的としており、言い換えると、被疑者は処分が決まると示談金を支払おうとすることは、まずありません。
処分が決まった後で、被害者が被疑者に民事の損害賠償請求をすればいいのではないか、とも思われますが、示談交渉と比べると、時間も労力も使いますし、被疑者が損害賠償金を支払うことも確実ではありません。
そうすると、被疑者が被害者に示談金を支払う姿勢を示しているうちに、示談交渉に応じる方がいいということなります。
勾留中の被告人との面会
新しい年を迎えて早々、大きな災害、事故、事件が続き、不安なお気持ちになられている方もいらっしゃるかと思います。
皆様の今年一年の安寧とご多幸をお祈り申し上げます。
ところで、私が弁護士として現在担当する事件に、留置施設に勾留されている被告人の私選弁護人として、刑事弁護をするものもあります。
その場合、弁護人は、勾留中の被告人と、留置施設の接見室で、原則としていつでも、職員の立ち合いがない状態で、面会することができます。
その際、弁護人は、被告人に刑事手続の流れを説明し、取調べの内容を聴いて今後の取調べへの対応についてアドバイスをするなどします。
また、弁護人は、その際、被告人に家族や同僚からのメッセージを伝えたり、被告人から家族や同僚へのメッセージを受け取ったりもしています。
一方、弁護人以外の人が勾留中の被告人と面会する場合、弁護人とは異なり、多くの制限があります。
例えば、大阪府警の管理している留置施設だと、一般的には、留置施設で面会できる時間は平日の朝から昼頃、昼休みをはさんで昼頃から夕方頃までの間の20分間程度の時間に限定されており、休日は面会することができません。
また、被告人と面会することができる人も、1日1組に限定されています。
そして、被告人と面会する時には、留置施設の職員の立ち会いがあります。
さらに、被告人に対し、接見禁止の処分がなされた場合、弁護人以外の人は被告人と面会することができません。
なお、大阪府警察ホームページには、弁護人以外の人が留置施設で面会する時の遵守事項として、以下の事項が挙げられています。
● あらかじめ告げられた時間内に面会を終了すること
● 録音機、カメラ、ビデオカメラ、携帯電話、パーソナルコンピュータ等を使用してはなら
ないこと
● あらかじめ申し出て承認を受けた場合を除き、外国語、隠語等を使用しないこと
● 必要がある場合には、職員が着衣若しくは携帯品を検査し、又は携帯品を一時預かること
があること
● 留置施設の職員の指示に従うこと
● 遵守事項に違反する場合には、面会を一時停止し、又は終了することがあること
その他、被告人や留置施設の事情で、被告人と面会ができなかったり、面会まで時間がかかったりすることもあります。
ですので、被告人と面会する前に、あらかじめ弁護人に相談をするほか、留置施設のある警察署に問い合わせをしたりして、被告人との面会について時間やルール等を事前に確認しておくことをお勧めします。
刑事事件の弁護士費用特約について
刑事事件やその他の事件について、大阪の事務所でご相談を受けるほか、電話でご相談を受けて弁護活動をする日々を送っています。
その際、自動車で交通事故を起こしたことについてご相談を受けていた方から、弁護士が刑事弁護を受任した後に刑事弁護の費用を支払う際、加入している損害保険の弁護士費用特約を利用し、保険金で支払いたいというお話を受けました。
損害保険に加入しておけば、もし交通事故を起こしてしまった場合に、事故の被害者に支払う損害賠償を、保険でカバーすることができます。
その損害保険に、刑事弁護の費用についてもカバーすることができるという弁護士費用特約があることをよく知らなかったので、インターネットを検索するほか、損害保険を実際に取り扱う損害保険会社に問い合わせるなどして、弁護士費用特約について調べてみることにしました。
調べてみると、確かに、損害保険会社が販売する損害保険には、弁護士費用特約が付されているものがあります。
そして、弁護士費用特約の中には、交通事故によって被保険者がけがをしたり、自身の自動車や家屋等を壊されたりして被害者になった場合に、事故の相手に対して損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や、法律相談の費用等を保険金として支払うものがあります。
それだけではなく、交通事故によって被保険者が他人にけが等をさせて加害者になった場合にも、刑事事件の対応を行うために支出された弁護士費用や法律相談の費用等を保険金として支払うという特約のある保険を、少数ですが見つけることができました。
今回のご相談者さんが加入されている損害保険の弁護士費用特約でも、刑事事件の弁護士費用について、保険金として支払いを受けることができそうです。
とはいえ、飲酒運転や無免許運転をして事故を起こした場合や、わざと事故を起こした場合など、弁護士費用特約の適用はなく、刑事弁護の弁護士費用が保険金として支払われない場合もあるようです。
また、そもそも交通事故によって加害者になった場合の特約ですので、その他の罪を犯した場合には、当然ながら弁護士費用の特約はないことになります。
そうすると、刑事弁護の費用を保険金で支払いたいというご相談を受けるのは、交通事故を起こした加害者からの場合にとどまることになるのでしょう。
教師による体罰と懲戒
ここ最近、弁護士が学校内で起こる様々な問題を解決するため、スクールロイヤー制度が設けられるところが増えてきています。
大阪府でも大阪弁護士会と連携してスクールロイヤー制度が導入されており、子どもに関する問題に詳しい大阪弁護士会所属の弁護士が、スクールロイヤーとして登録されているとのことです。
ところで、学校内で起こる問題の一つとして、教師による児童・生徒に対する体罰の問題があります。
学校教育法11条は、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、…児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えてはならない。」と規定して、教師による懲戒を認める一方、体罰を禁止しています。
文部科学省は、平成25年3月13日付けで「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について」という通知を発しています。
同通知は、体罰について、児童・生徒の心身に深刻な悪影響を与え、教員等及び学校への信頼を失墜させる行為であること、体罰により正常な倫理観を養うことはできず、むしろ児童・生徒に力による解決への志向を助長させ、いじめや暴力行為などの連鎖を生むおそれがあることを挙げて、児童・生徒への指導に当たり、いかなる場合も体罰を行ってはならない、としています。
一方、学校教育法11条は、教師が懲戒を加えることを認めています。
そこで、懲戒と体罰との区別が問題となります。
この点、文部科学省は、前記通知等により、教師が児童・生徒に対して行った懲戒行為が体罰に当たるかどうかは、児童・生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考えて、個々の事案ごとに判断する必要があるとしています。
その上で、①殴る、蹴る、突き飛ばす、物を投げつけるなど、身体に対する侵害を内容とするもののほか、②長時間にわたり正座させる、別室に留め置いてトイレに出ることも許さないなど、児童・生徒に肉体的苦痛を与えるようなものに当たるものについて、体罰に当たるとしています。
他方、文部科学省は、放課後に教室に居残りさせる、授業中に教室内で起立させる、課題や清掃活動を課す、当番を多く割り当てる、立ち歩きの多い児童生徒を叱って着席させる、練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学させるなどの行為は、肉体的苦痛を伴わない限り、懲戒として認められるとしています。
そうすると、教師が児童・生徒に対して殴る、蹴る、長時間にわたり正座させる、別室に留め置いて外に出さない行為等について、学校教育法で禁止されている体罰に当たるうることになります。
そのような体罰に当たりうる行為は、傷害罪や暴行罪、監禁罪等の構成要件に該当しますので、教師には刑事責任が問われる可能性があります。
もっとも、教師が児童・生徒に対してそのような体罰に当たりうる行為を加えたとしても、場合によっては教師に刑事責任が問われない可能性があります。
例えば、児童・生徒が教師の指導に反抗して教師の足を蹴ってきたので、教師がその背後に回ってその身体をきつく押さえた場合のように、教師が防衛のためにしてやむを得ずしたような場合には、正当防衛が認められ、教師は刑事責任を免れる可能性があります。
また、他の児童・生徒を押さえつけて殴っていた児童・生徒の身体をつかんで引き離した場合のように、他の児童・生徒に対する暴力行為を制止するような場合にも、正当防衛や正当行為が認められ、教師は刑事責任を免れる可能性があります。
文部科学省も、前記通知により、先ほど挙げたような場合には体罰に当たらず、正当防衛又は正当行為として刑事責任を免れうるとしています。
在宅事件のご相談
おかげさまで、大阪で弁護士になってから、刑事事件についてのご相談を受ける機会があります。
ご相談の内容は、警察に呼ばれたり捕まったりしていないが、自分のしたことが犯罪に当たるかどうか気になるというものや、知り合いが警察に捕まってしまったがどうしたらよいかというもののほか、自身が警察に呼ばれて取調べを受け、身柄拘束されずに帰されたが、今後どうしたらよいかというものもあります。
事件の被疑者が警察に呼ばれて取調べを受けたが身柄拘束されていないものは、在宅事件と呼ばれます。
一方、被疑者が逮捕され、身柄拘束された事件のことは身柄事件と呼ばれます。
刑事訴訟法によれば、身柄事件では、被疑者は逮捕される際、被疑事実の要旨が記載された逮捕状を示されます。
また、勾留された際に出された勾留状にも被疑事実の要旨が記載されますので、弁護士は、逮捕状に記載された被疑事実を被疑者に確認したり、勾留状の謄本を入手して被疑事実を確認したりして、事件の内容を把握することになります。
一方、在宅事件では、逮捕状も勾留状もありません。
ですので、弁護士は、事件の内容を被疑者の話す内容から判断することが必要になります。
例えば、被疑者が話す事件に至る経緯や事件の経過を聴くことによって、被疑者が事件の内容についてどのようにとらえているかがわかります。
また、私の前職が検察官だったこともあり、被疑者から、警察からどのような質問を受けたか、差押えを受けたものはあるか、警察官と一緒に現場や関係場所に行ったかなど、警察に呼ばれて取調べを受けたときに体験した内容を聴くことで、警察がその事件をどのようにとらえているか、その事件の捜査がどの程度まで進んでいるかなどがわかります。
さらに、私の前職が検察官だったこともあり、先ほどまでお話しした事情のほか、被疑者の前科前歴関係や家族、仕事等の、被疑者の身上関係等も確認することで、被疑者が受けるだろう刑事処分も、ある程度予想することができます。
弁護士は、被疑者からご相談を受けた際は、被疑者からそれらの事情をよく聞いた上、事件の概要や今後予想される捜査の流れ、被疑者が受けるだろう刑事処分等について判断します。
それを踏まえて、弁護士は、警察官や検察官による取調べの対応、被害者との示談など、今後起こりうることについて広くアドバイスをします。
また、その中でご依頼を受けることになれば、弁護人に就任し、被疑者のために弁護活動を開始することになります。
ご自身はもちろん、身の回りで、警察に呼ばれて取調べを受けて、今後どうなるのか、どうすればよいのかなどと不安を感じられている方がおられたら、一度、弁護士へご相談されることをおすすめします。
飲酒による交通事故の刑事責任
飲酒した後で自動車を運転して人身事故を起こした場合、従来は、酒気帯び運転という道路交通法違反のほか、業務上過失致死傷、その後改正されて現在は過失運転致死傷の刑事責任に問われていました。
しかし、飲酒による人身事故が悪質な犯罪であるという社会的な認識の高まりもあって、ここ最近、刑法や道路交通法の法改正が相次いでおり、現在はより重い危険運転致死傷罪に問われる可能性もあります。
危険運転致死傷罪は、故意に危険な運転行為を行った結果として人を死傷させた行為について、暴行により人を死傷させる傷害罪や傷害致死罪に準じ、故意犯として処罰するものです。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号は、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」によって人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処すると、危険運転致死傷罪を規定しており、法定刑については、過失運転致死傷(7年以下の懲役、禁錮又は100万円以下の罰金)と比較して相当重くなっています。
「アルコール…の影響により正常な運転が困難な状態」というのは、酒類の影響により、道路及び交通状況等に応じた的確な運転操作を行うことが困難な心身の状態をいいます。
例えば、飲酒した影響で、思ったとおりにハンドルやブレーキ等を操作することや、前方を注視してそこにある危険を的確に把握し対処することが、現に困難な状態が、そのような状態に当たるとされています。
また、同法3条1項は、危険運転致死傷罪の別類型として、「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障を生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する」と規定しており、法定刑についても、過失運転致死傷と比較して相当重くなっています。
「アルコール…の影響により、その走行中に正常な運転に支障を生じるおそれがある状態」とは、酒類の影響により、自動車を運転するのに必要な注意力、判断能力又は操作能力が相当程度減退している状態、あるいは、そのような状態になり得る具体的なおそれがある状態をいいます。
例えば、道路交通法の酒気帯び運転に該当する程度のアルコールを身体に保有している状態であれば、通常はそのような状態に当たるとされています。
また、同法3条1項の危険運転致死傷罪の故意として、「アルコール…の影響により、その走行中に正常な運転に支障を生じるおそれがある状態で、自動車を運転」することの認識が必要とされています。
すなわち、身体にアルコール等を保有していることの認識と、その影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態にあることの認識を要し、かつ、それで足りるとされています。
具体的には、客観的に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態にあったと認められる限り、酒気帯び運転に該当する程度のアルコール等を身体に保有していることを認識していれば、危険運転致死傷罪の故意を認めることに十分であるとされています。
そうすると、道路交通法の酒気帯び運転に該当する程度のアルコールを身体に保有している状態で、その状態にあることを認識して自動車を運転した場合、すなわち、それなりに飲酒した後で自動車を運転した場合、人身事故を起こすと、法定刑が相当重い、同法3条1項の危険運転致死傷罪によって処罰される可能性があるということになります。
どのような犯罪が成立するにしても、飲酒して自動車を運転し、人身事故を起こすことは処罰の対象になります。
自分は人身事故を起こすわけがないと信じていたとしても、自動車の飲酒運転は絶対にしないようにしましょう。
また、もし自動車の飲酒運転をして人身事故を起こした場合、重い刑罰を受ける可能性があるほか、民事の損害賠償の問題にもなりますので、早めにお近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。