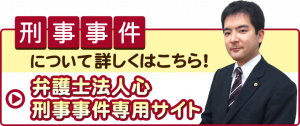- トップ
- ブログ
ブログ
控訴の手続き
大阪の地裁で審理され、刑事事件の弁護士として活動していた事件の判決について、その内容が承服できないものだったため、被告人である依頼者と協議の上、高裁に控訴しました。
地裁の判決の際にも裁判官から告知されますが、控訴するまでの期限は、判決の翌日から起算して14日間です。
その間に、弁護人は、被告人と話し合って控訴をするかどうかを決めることが必要になります。
そして、控訴することになった場合、高裁にあてた控訴申立書を、地裁の刑事訟廷に提出することになります。
その際、第1審の弁護人は、その権限で控訴することができます。
また、被告人自身も控訴することができます。
控訴申立書は決められた書式のものがあり、概ね、第1審の判決内容には不服なので控訴するという内容が記載されています。
控訴申立書には、控訴するに至った理由や経緯等について記載する必要がありません。
ところで、第1審の弁護人は、控訴申立てをするまでは被告人からの委任の範囲内ですが、その後の手続は範囲外になります。
ですので、第1審の弁護人が引き続き控訴審の刑事弁護を担当する場合、被告人から控訴審の弁護人として改めて選任を受ける必要があります。
その場合、控訴審の弁護人選任届を裁判所に提出する必要があります。
改めて控訴審も弁護人として活動することになれば、控訴趣意書の作成にとりかかることになります。
控訴趣意書は、第1審の判決内容に誤りがあり、控訴審で是正させるべきであることを詳細かつ論理的に主張する書面であり、控訴趣意書を作成することが、控訴審における弁護活動の中心になります。
控訴趣意書の提出期限は、控訴審の裁判所から提示されますので、その期限までに作成する必要があります。
もし、期限に間に合わなければ、控訴が棄却され、控訴が認められなくなってしまいます。
ですので、提出期限に間に合わないことが見込まれれば、期限までに期限の延長申請をしておく必要があります。
現在、第1審の判決内容を検討しつつ、控訴趣意書の内容を詰めているところです。
保釈決定の効力と再保釈の請求
大阪で弁護士として活動している中で、刑事事件の被告人の弁護人として保釈請求をし、保釈決定を得たことがありました。
保釈決定は、裁判で懲役や禁錮の判決宣告を受けた時点で失効します。
すなわち、保釈されている被告人が裁判で実刑判決を受けた場合、保釈の効力が失効するので、被告人は判決言渡し直後に収容されることになります。
保釈されている被告人が実刑判決を受けることが予想される場合、裁判所には、被告人を収容するために検察庁の職員が来て、収容の準備をしていることがあります。
なお、保釈されている被告人が裁判で無罪や刑の全部の執行猶予、罰金、科料等の判決を受けた場合、勾留状が失効しますので、被告人が判決言渡し直後に収容されることはありません。
ところで、実刑判決が予想される場合で、かつ、被告人が実刑判決を不服として控訴する意向があると考えられる場合、弁護人としては、判決後速やかに再保釈を請求することができるよう、改めて保釈の準備をしておく必要があります。
再保釈の請求は、控訴申立て前に一審弁護人の地位で行うことができます。
仮に、控訴申立て後の場合だと、すでに一審弁護人の立場が失われてしまっているので、被告人から新たに弁護人選任届を受け取る必要があります。
なお、再保釈の請求は、控訴する前、または控訴した後、訴訟記録が控訴した裁判所に到達するまでは一審の裁判所へ、控訴審の裁判所に移った後は控訴審の裁判所に対して行います。
再保釈が認められる場合、保釈保証金が増額されます。
もっとも、保釈保証金は最初の保釈の際に裁判所に納めた分がありますので、実際は増額した分を追加で裁判所に納めることになります。
また、一度保釈が認められているからといって、再保釈が必ず認められるわけではありません。
再保釈の判断については、控訴審で現判決が破棄される見込みや、保釈を必要とする緊急の必要性の有無や程度、逃亡のおそれの大小という点が考慮されるといわれています。
少年事件の手続
弁護士として大阪でご相談を受けている際に、未成年が被疑者になる刑事事件の相談を受けたことがありました。
未成年による刑事事件は、少年事件と呼ばれ、成人による刑事事件とは別に、少年法によって手続等が規定されています。
捜査段階では、少年は成人と変わらず、警察官や検察官による取調べを受けるなどして、事件に対する捜査が行われます。
また、少年も、成人と同様に逮捕され、留置施設に勾留されるなど、身柄を拘束されることがあります。
なお、少年については、身柄を拘束される際に、勾留に代わる観護措置が講じられることがあります。
勾留に代わる観護措置では、少年鑑別所で10日間観護措置を受けます。
捜査が終わると、原則として、少年事件は全部の事件が家庭裁判所に送致されます。
成人の事件だと、起訴猶予や嫌疑不十分などの理由で不起訴処分になり、起訴されないことも多々ありますので、原則として家庭裁判所に送致されることは、少年事件の手続の大きな特徴です。
これに関して、被害者のいる事件での弁護活動として示談交渉が行われることが多く、成人の事件では示談交渉がまとまると起訴猶予により不起訴処分になることがよくあるのに対し、少年事件では示談交渉がまとまったからといって家庭裁判所に送られないことは、基本的にありません。
ですので、成人事件では示談交渉を捜査段階の間に早急にまとめることも多いのですが、少年事件では、形だけの被害弁償を急ぐよりも、少年自身の真の反省や謝罪の気持ちを十分に引き出し、それに基づいた示談交渉をすることが重視されます。
家庭裁判所に送致されると、少年鑑別所に収容されて、通常4週間の観護措置がとられることがあります。
また、家庭裁判所調査官により、少年や保護者または関係者の行状、経歴、素質、環境等について調査が行われます。
その上で、少年審判が行われ、少年の処分が決められます。
少年審判では、原則として検察官が立ち会うことはなく、裁判所が自ら主導して事件の調査や審理を行います。
少年の処分は、保護処分として少年院送致、児童自立支援施設等送致、保護観察又は不処分のいずれかになります。
なお、一定の重大な犯罪の場合や少年が成人になった場合は、少年に成人の刑事裁判を受けさせるために、検察官送致の処分がされることがあります。
被告人質問について
最近、弁護士として大阪で依頼を受けた被告人について、被告人質問を行いました。
被告人質問は、刑事裁判の手続において、被告人に対して弁護人、検察官及び裁判官が質問をする手続です。
被告人にとっては、質問に対する回答という形式ですが、起訴された事実について、認否をした後で詳しく具体的に主張することができる唯一の機会になります。
仮に、起訴された事実を否認するなどして犯罪の成立を争うような場合には、被告人が主張する筋立て(いわゆるアナザーストーリー)にそう内容を被告人質問で詳細に述べる必要があります。
そのためには、事前に被告人と弁護人との間で、どのような筋立てをするのか、その筋立てにそって弁護人がどのような質問をして、被告人がどのように回答するのか、検察官や裁判官からの質問を予想してどのように答えるのがよいのか、などについて、繰り返して何回も打ち合わせをする必要があります。
特に、被告人が勾留されている場合には、弁護人が接見する機会にしか打ち合わせをすることができないので、被告人にとって相当な負担になります。
一方、起訴された事実を認める場合でも、事前に被告人と弁護人との間で、被告人質問について綿密に打ち合わせをしておく必要があります。
そのような場合でも、事実関係を争わないにしても、被告人に有利な情状があることを裁判で明らかにする貴重な機会であることには変わりがありません。
被告人に有利な情状としては、例えば、事実関係を認めて反省をしていること、弁償や示談の話し合いが行われていること、同じような罪を再び犯すことがないように自動車の運転を控えたり運転免許を返納したりするなどの取り組みをしていること、社会復帰後に薬物依存の治療を受けたり薬物依存からの回復をサポートする団体に入ったりすることといった内容が挙げられます。
また、検察官や裁判官からの質問を予想してどのように答えるのがよいのかを検討しておくことは、そのような場合でも大事なことになります。
贖罪寄付について
大阪弁護士会館には弁護士ごとにポストが設けられており、私も、大阪弁護士会館に行くついでにポストに何か入ってないかを確認することがあります。
ある日、ポストの中を確認すると、大阪弁護士会から、贖罪寄付の利用を呼び掛けるチラシが入っていました。
贖罪寄付は、被害者のいない犯罪や、被害者がいても処罰感情がとても強く、示談はおろか被害弁償金の一部でも受け取ってもらえないような場合に、示談金を支払う代わりに寄付をすることを言います。
贖罪寄付は、日弁連をはじめ、大阪弁護士会などの各地の弁護士会、日本司法支援センター(法テラス)、日弁連交通事故相談センターや各地にある更生保護施設、犯罪被害者支援団体や薬物等依存者自助グループなどで受け付けられています。
先ほどの大阪弁護士会のチラシによれば、「刑事贖罪寄付金は日本弁護士連合会及び当会(引用者注・大阪弁護士会)の法律援助事業基金に充当されます。当会においては委託援助事業への上乗せ加算及び当会の自主援助事業の財源として利用されます。」と、日弁連や大阪弁護士会による法律援助事業の財源になることが書かれています。
具体的な法律援助事業の対象は、犯罪被害者や子ども、難民、外国人及び高齢者、障害者、ホームレス等であるそうです。
そして、同じチラシによれば、「事件への反省を込めてなされる贖罪寄付は情状の資料として評価されています。」と、贖罪寄付をすることで被疑者の処分や被告人の刑罰について有利に評価されることが書かれています。
実際には、贖罪寄付は、示談が成立して示談金を支払う場合ほどには有利に評価されるものではないようですが、一定程度、被疑者や被告人に有利に評価されるようです。
もっとも、被疑者や被告人が贖罪寄付をするにしても、弁護士や周囲の人に贖罪寄付を勧められて、勧められた寄付先に寄付をした、というのであれば、主体的に考えて贖罪寄付をしたとはいえず、被疑者や被告人にそれほど有利に働くものではないと思います。
例えば、スーパーでの万引きの事件で、スーパーが運営会社の方針として示談や被害弁償を受け付けないことになっていて示談や被害弁償ができないので、せめてスーパーの運営会社が行っている慈善事業に寄付をしたいとしてその慈善事業の財団に寄付することにしたといった経緯について、被疑者や被告人が自身で説明できるようにしておく必要があるように思います。
保釈許可決定が出た後の流れ
刑事弁護の依頼を受けていた事件に関し、大阪地方裁判所に対し、被告人の保釈請求をしたところ、保釈許可の決定を得ることができました。
保釈許可の決定が出たからといって、自動的に被告人の身柄が解放されるわけではありません。
ここでは、弁護士としての備忘録も兼ねて、大阪地方裁判所で保釈許可の決定が出た後の流れについてまとめておきます。
保釈許可の決定が出ると、裁判所からその旨連絡を受けますので、弁護人は、裁判所の公判係属部の事務室で、保釈許可の決定書と、保釈保証金を納める際に提出する保管金提出書を受け取ります。
また、弁護人は、被告人の家族にも連絡を取る必要があります。
被告人の家族は、被告人のことをとても心配し、一日でも早く身柄を解放するように求めていました。
他方、被告人の家族に、保釈保証金の用意や、身柄が解放された後の被告人の迎えを準備してもらうためにも、連絡を取る必要があります。
その後、被告人の家族に用意してもらった保釈保証金を受け取り、裁判所の出納第一課まで行き、先ほどの保管金提出書と共に保釈保証金を提出しました。
出納第一課では、繰り返し、計数機を使うなどして保釈保証金が数えられ、保釈保証金の額に間違いがないことを確認された後、保釈保証金を預かったことを証明する保管金受領証書を受け取りました。
保釈保証金は、判決が確定すれば還付されますが、それまで、保管金受領証書は大切に保管しておかなければなりません。
なお、裁判所は、通常、午後5時で執務が終わるので、午後5時を過ぎると保釈保証金を預かってもらえなくなる可能性があります。
そうなると、被告人の釈放が翌日以降にずれこむことになります。
そこで、午後5時を過ぎてから保釈保証金を持ち込む可能性がある場合、あらかじめ裁判所に対し、その旨連絡し、出納第一課の方々に待っていてもらうように頼んでおく必要があります。
今回も、保釈保証金を用意して裁判所に持ち込む時間が午後5時を過ぎる可能性があったので、あらかじめ、裁判所に対してそのことを連絡し、出納第一課の方々に待ってもらっていました。
また、事前に登録しておくと電子納付の手続で保釈保証金を納めることも可能ですが、その際も、午後5時を過ぎて電子納付の手続を取ると、事務手続きが翌日扱いとなり、被告人の釈放が翌日以降にずれ込むことになります。
保釈保証金の納付が確認された後、裁判所から検察官にその旨の連絡がなされます。
その際、検察官は、被告人を釈放する旨の指揮をします。
その指揮を受けて、初めて被告人の身柄は解放されます。
被告人は、待っていた家族と合流し、久しぶりに自宅に帰ったのでした。
保釈請求について
先日、刑事弁護の依頼を受けていた事件に関し、大阪の裁判所に対して、被告人の保釈請求をしました。
保釈は、弁護士が、被告人の身柄を解放するために行うことができる手続の一つであり、勾留中の被告人が、保証金を納めることで身柄拘束を解いてもらうことができるというものです。
弁護人は、裁判所に対し、勾留中の被告人について、法律上、保釈することができない事情がないことのほか、裁判所の裁量によって保釈することが相当であることを理由に挙げて、保釈を請求します。
裁判所は、保釈の請求を受けた後、検察官に対し、被告人について保釈の請求があったことを通知し、意見を求めます。
それに対し、検察官は、被告人を保釈することについて意見を返します。
通常、検察官は、被告人を保釈することについて「不相当」か「相当」、又は「しかるべく」と意見を返します。
「しかるべく」というのは、裁判所の判断に任せるという意味です。
また、検察官は、「不相当」の意見を返す場合には、その理由を明らかにします。
その場合、検察官は、勾留中の被告人には法律上、保釈することができない事情があることや、裁判所の裁量によっても保釈することが相当ではないことを理由に挙げて、保釈をしないように意見することが通常です。
裁判所は、検察官の意見を受けて、保釈を許可するかを決定します。
裁判所が保釈を許可した場合、納める保証金の額も併せて決められます。
保証金の金額は、100万円単位になることが多いです。
また、その場合、被告人の制限住居や面会相手の制限等の条件についても、併せて決められます。
被告人は、保証金が納付されると釈放されます。
一方、保釈が許可されなかった場合には、弁護人は、裁判所に不服を申し立てることができます。
その場合、裁判所が決定した保釈の不許可について、維持すべきか又は取り消して被告人に保釈を許可すべきかどうかについて、より上位にある裁判所が再び判断をすることになります。
その結果、裁判所の判断が覆り、保釈が許可される可能性があります。
まとまった金額の保証金を用意する必要はありますが、被告人の身柄拘束を解く手段として、弁護士による保釈請求はよく利用されています。
交通事故の公判弁護
先日、大阪の裁判所で行われた、交通事故の刑事裁判で、公判弁護をしました。
事実関係自体には争いなく、公判は1回で結審しました。
とはいえ、弁護士としては、依頼を受けた被告人に少しでもプラスになる情状を公判で示し、マイナスになる情状についても少しでもフォローして、執行猶予付きの判決など、被告人に少しでも有利な判決を求める必要があります。
そのためには、事前に被告人とよく打ち合わせをするなどして、事前準備をする必要があります。
例えば、被告人に有利な情状として
〇 交通事故を起こした時に運転していた自動車を廃車にした
〇 運転免許が取り消された
〇 交通事故でけがを負わせた人の治療代は、かけていた保険から出ている
〇 今後、同居の家族が、交通事故を起こさないように被告人を監督する
といった事情が挙げられる場合、それぞれ証拠を用意する必要があります。
例えば、被告人が事故車両を廃車したのであれば、事故車両の廃車証明や抹消登録、被告人が運転免許を取り消されたのであれが、公安委員会が発行した運転免許の取消決定書を用意する必要があります。
また、交通事故の被害者に対する支払いの関係では、被告人がかけていた損害保険の証券や、損害保険会社が発行した支払いの明細書といった書類を用意する必要があります。
そして、家族による監督の関係では、監督してもらう家族に、今後被告人を監督することを約束する内容の手紙を書いてもらうことや、証人として、被告人を監督することを裁判で証言してもらうことが考えられます。
家族に証人として出てもらう場合は、事前に家族に証人として出てもらうことについて承諾を得たうえ、証人尋問ではどう話せばよいかについて打ち合わせをしたり、予行練習をしたりしておくことが必要になります。
さらに、被告人とは、被告人質問について打ち合わせをし、弁護人が質問しておく内容のほか、検察官や裁判官から質問されると思われる内容についても、どのように話をすればよいか、予行練習しておく必要があります。
そのような事前準備を経て、公判弁護に臨むことになります。
不起訴処分と起訴猶予について
刑事弁護の依頼を受けていた刑事事件の被疑者が不起訴処分になりました。
不起訴処分になると、検察官から被疑者が不起訴処分になったという内容の告知書を受け取ることができるため、被疑者を担当していた検察官に連絡して、被疑者の不起訴処分の告知書の発行を依頼しました。
すると、数日後、検察官から、検察庁の書式による、不起訴処分告知書が送られ、被疑者が不起訴処分になったことを、書面でも確認することができました。
被疑者が不起訴処分になったことにより、弁護士として依頼を受けた責任を果たすことができたと思っています。
ところで、不起訴処分とは、検察官が行う処分のうち、被疑者を起訴しないという処分を言います。
そして、不起訴処分になる理由の多くは、起訴猶予になります。
起訴猶予というのは、犯罪を認定する事実が明らかな場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により、被疑者を起訴する必要がないと検察官が判断した場合のことを言います。
検察官が起訴猶予にするかどうかについては、そのような被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況等をよく検討して、判断することになります。
検察官が起訴猶予の判断をするに当たって、犯罪後の情況に関する事柄については、被疑者の反省の有無、謝罪や被害回復の努力、又は逃亡や証拠隠滅の行動、環境の変化、社会的制裁の有無、身柄引受人その他の将来被疑者を監督する者や保護者の有無などの、環境調整の可能性の有無のほか、被害弁償の有無や示談の成否、被害感情等が問題となります。
今回の事件では、大阪の事務所から出て被害者と会うなどして示談交渉をして、被害者との間で示談を取りまとめることができましたが、示談の成否は、先ほど述べた事情の中では犯罪後の情況に関係することになります。
今回の事件に限りませんが、被害者がいる犯罪では、被害者との示談は、検察官が起訴猶予するかどうかを判断する際に、重視されるところであり、刑事弁護でも力が入れられているところです。
被害者との示談交渉も含めて、刑事事件の弁護について気になる点がありましたら、お気軽にご相談ください。
示談交渉を持ち掛けられたら
被害者との示談交渉は、刑事弁護人の重要な役割の一つです。
刑事弁護人の立場からすると、被害者との示談をまとめることで、被疑者の処分を免れ、又は軽減させることを目的としており、そのために被害者に大阪の事務所まで来てもらったり、被害者の許に伺ったりして示談に関するお話しをすることになります。
一方、被害者の立場からすると、これまで被害に遭わせた犯人を許せないと思っていたところ、弁護士から示談してほしい、犯人を許してほしいなどと持ち掛けられるのですから、どうすればいいのやら困惑することもあると思います。
実際に、私も、検察官だった時、捜査や公判を担当していた被害者から、弁護士から示談を持ち掛けられたけれど、どうすればよいかなどと相談を受けたことが何度もありました。
その際、私は、検察官という公務員の立場で示談を勧めたり勧めなかったりすれば中立性を害してしまうので、示談を勧めたり勧めなかったりするような回答はしませんでした。
もっとも、被害者が示談に応じれば受け取る示談金は、民事事件でいえば不法行為に基づく損害賠償に当たるものですので、被害者が示談に応じた上で示談金を受け取ることは当然のことであり、問題がないことはお話ししていました。
そのような話は、私に限らず、多くの検察官がお話ししていたと思います。
また、私がそのようにお話しすると、多くの被害者から、示談に応じれば犯人に有利になってしまうのではないか、犯人が不起訴になってしまうのではないか、などとご質問を受けることがありました。
確かに、検察官の立場からしても、示談がまとまることで被疑者が不起訴になるかどうかはともかく、被害者に謝罪も弁償もせずに放置しているよりも、示談により謝罪や弁償をする方が、被疑者には有利になることは、そのとおりです。
私は、被害者に対して、示談がまとまることで被疑者に有利になる可能性があること、その上で示談交渉に応じるかどうかは自由であることをお話ししていました。
では、弁護士の立場だと、被害者から示談交渉に応じるべきか相談を受けたらどう答えるべきでしょうか。
通常は、被害者のお考えやお気持ちをよく伺って、それに沿ったお答えをすることになるのでしょうが、私なら、示談交渉に応じる方向でお答えするのだろうと思います。
なぜなら、被疑者が被害者との示談をまとめようとするのは、被疑者の処分を免れ、又は軽減させることを目的としており、言い換えると、被疑者は処分が決まると示談金を支払おうとすることは、まずありません。
処分が決まった後で、被害者が被疑者に民事の損害賠償請求をすればいいのではないか、とも思われますが、示談交渉と比べると、時間も労力も使いますし、被疑者が損害賠償金を支払うことも確実ではありません。
そうすると、被疑者が被害者に示談金を支払う姿勢を示しているうちに、示談交渉に応じる方がいいということなります。
月別アーカイブ
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒530-0001大阪府大阪市北区
梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル 30F
0120-41-2403