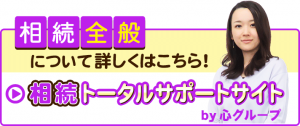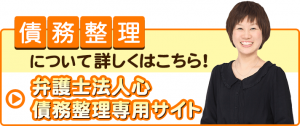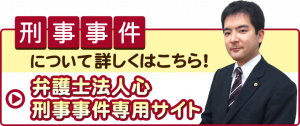犯罪被害者等給付金の制度
現在、犯罪被害者等給付金の請求を準備しているところです。
犯罪によって被害を受けた場合、極端な例だと亡くなられた場合、犯罪被害者やそのご遺族は、本来、加害者から被害弁償を受けるべきものです。
しかしながら、加害者に財産がないために被害回復が十分にできない場合や、加害者の財産が発見困難であり差し押さえができない場合などがあり、加害者から十分な被害弁償を受けることができない場合があります。
また、犯罪被害者は治療を受け、仕事を休業するなどして、収入が減る一方で支出が増え、予想外に経済的負担を強いられることになります。
ご遺族も同様に、亡くなられた犯罪被害者が一家の大黒柱であった場合には、その経済的な損失は甚大なものになります。
そこで、国が、加害者に成り代わり、犯罪被害者やそのご遺族に対して、一時金を支給する制度として、犯罪被害者等給付金の制度があります。
犯罪被害者等給付金には、重傷病給付金、障害給付金及び遺族給付金の3種類があります。
重傷病給付金は、一定以上の重い傷害や疾病を負った犯罪被害者に対し、医療費や休業損害を考慮して算出した額を支給するものです。
障害給付金は、傷害又は疾病が治った時に障害が残った犯罪被害者に対し、その障害の程度に応じて算出した額を支給するものです。
遺族給付金は、犯罪被害者のご遺族に対し、犯罪被害者の収入と、その収入によって生計を維持していたご遺族の人数に応じて算出した額を支給するものです。
犯罪被害者等給付金は、犯罪被害者の住所地を管轄する都道府県の公安委員会に申請し、その裁定により支給を受けることになっています。
例えば、犯罪被害者が大阪府内に住んでいれば大阪府公安委員会(実際の窓口は大阪府警察本部になります。)に申請して、その裁定により支給を受けることになります。
大阪府の場合、申請から裁定までの期間として、概ね半年程度を要しているようです(以上につき、大阪弁護士会犯罪被害者支援委員会編・犯罪被害者支援マニュアル参照)。
令和3年度に、全国で犯罪被害者等給付金の支給を受けた犯罪被害者は288人、総額は約10億888万円でした(令和4年版犯罪白書参照)。
このように、犯罪被害者等給付金の制度は、全国的にもそれほど多くは利用されているとは言い難い制度ではありますが、給付金の支給を受けることにより、犯罪被害者やそのご遺族のご負担が少しでも緩和されるように活用されればと思い、私も請求の準備をしているところです。